1. はじめに:なぜ打ち合わせが成功のカギになるか
Shopify を使った Web 制作・デザイン案件では、技術力やセンスだけでなく「クライアントとの認識合わせ」が非常に重要になります。なぜなら、デザインの好み、機能要件、予算、スケジュール感などのズレが後から大きな手戻りを生みやすいからです。
クライアント側は “お店を作りたい/売上を上げたい/見た目を良くしたい” という漠然とした願望を持っていることが多く、それを具体的な仕様に落とし込むのが私たち制作者の役割です。
この “落とし込みの精度” が高いか低いかで、後の調整コスト・トラブル率・納期遵守などがかなり変わってきます。
だからこそ、打ち合わせというフェーズを軽視してはいけません。ここで認識齟齬をできる限りなくす体制を作ることが、成功する案件と炎上する案件の分かれ道です。
【2025年最新】Shopify構築の料金相場はこちらの記事で解説しております↓

2. 打ち合わせ前の準備/資料・リサーチ
打ち合わせを始める前に、資料を揃えたり情報を調べたりする “先行投資” は、時間をかける価値があります。以下、準備しておきたいことをリスト化します。
2‑1. クライアントの事業・業界リサーチ
- クライアントの業界、競合ショップを把握しておく
- 既存の Web サイト(あれば)、商品のラインナップ、価格帯、ブランドイメージ
- 既に Shopify を利用している事例(似た業界)をピックアップ
- クライアントのビジネスモデルや収益構造(利益率、原価比率、物流コストなど)
こうした背景知識があれば、ヒアリング中の “なぜこの要件にしたのか” を深掘りできます。
2‑2. 制作体制・リソース確認
- 自分 or チームの技術スタック(Liquid・アプリ・テーマ経験など)
- 外部デザイナー・コーダーを起用するなら、その可否・単価・条件
- Shopify アドオン(外部アプリ)で既存の機能を賄えるかどうか
- 過去のテンプレート・基盤を使った応用可能性
2‑3. 事前ワークシート・仮設要件案の作成
クライアントに「こんな感じの機能を想定していますがどうでしょうか?」と提示できるように、ワイヤーフレーム案や機能一覧案(仮案)を用意しておきます。
項目例:
- トップページ、商品一覧・商品詳細、カート・チェックアウト、会員機能、レビュー機能、ブログ、FAQ、顧客センター、メルマガ連携など
- 決済手段(クレジット・コンビニ・キャリア決済など)
- 配送条件(送料無料ライン・複数配送先対応など)
- 在庫管理、複数倉庫、バリエーション、発送遅延対応
- SNS 連携、Instagram や TikTok の埋め込み、Shopify POS 連携など
この仮案があると、クライアント側も頭を動かしやすく、打ち合わせが具体的になります。
2‑4. 資料の体裁・テンプレート準備
- 打ち合わせ用スライドテンプレート(標準的な構成:目的、現状、要件、スケジュール、見積もり、リスクなど)
- 質問リスト(ヒアリング項目)
- 契約書・覚書テンプレート(機能・納品物・著作権・契約解除条件など)
- 議事録フォーマット
これらをあらかじめ用意しておくことで、打ち合わせ中に慌てずに対応できます。
こちらの記事でShopifyの魅力などを伝えております↓

3. クライアントへのヒアリング項目と設問例
実際に打ち合わせで聞くべき質問を整理します。以下は “漏れがちな項目” を含めたチェックリストと、それを引き出すための設問例です。
| 項目 | 質問例 | 注意点・深掘りポイント |
|---|---|---|
| 目的・目標 | 「この Shopify サイトを通じて、3か月後/1年後にどのような成果を目指しますか?」 | 売上・PV 数・顧客数など具体的に。 |
| 対象顧客(ペルソナ) | 「主な購入者層はどのような人ですか?(年齢・性別・ライフスタイルなど)」 | ペルソナがぼんやりしているとデザインや導線設計で迷う。 |
| ブランド・ビジュアルイメージ | 「参考にしたショップ・ Web サイトはありますか?」「色味・雰囲気で好きなもの・嫌いなものは?」 | 具体的な URL を出してもらうとミスマッチを減らせる。 |
| 機能要件 | 「検索・フィルター機能」「複数オプション(色・サイズなど)」「おすすめ商品レコメンド」「レビュー表示」など、仮案をもとに 「これは必須ですか?」「これはどうしますか?」とすり合わせる | “必須”/“あればいい” を明確にし、優先順位を聞く。 |
| 決済・配送条件 | 「どの決済手段を使いたいですか?」「代引き・後払い・定期購入は必要ですか?」「送料ルール(地域別送料・送料無料ラインなど)は?」 | 決済会社との連携可否やコストも踏まえて。 |
| 在庫管理・物流 | 「複数倉庫対応ですか?」「外部の在庫 API 連携が必要ですか?」「店舗在庫との併用はありますか?」 | 在庫関連は後工程で混乱しやすい。 |
| マーケティング連携 | 「メール配信システムは何を使いたいですか?」「LINE や Instagram の連携は必要ですか?」「SEO 対策やブログ運用はどうしますか?」 | マーケティング面での拡張性も意識しておく。 |
| 運用体制・更新 | 「更新を社内でやりますか?それとも依頼しますか?」「どのくらいの頻度でコンテンツ更新しますか?」 | 更新しやすい仕組みを設計するか、保守設計も考慮。 |
| 予算・スケジュール | 「この案件にかけられる予算の目安は?」「いつまでにローンチしたいですか?マイルストーンは?」 | 予算とスケジュールの整合性を早期に確認。 |
| リスク・制約 | 「既存データの移行はありますか?」「法令・規制・社内ルールなど制約はありますか?」「外部 API の制限やライセンス制限は?」 | 後からトラブルになる可能性を先に洗い出しておく。 |
ヒアリングの際、クライアントが曖昧な回答をすることが多いので、「〜というケースもありますが、どうしますか?」と仮案を示して選択を促すとよいでしょう。
4. デザイン・仕様すり合わせで注意すべきポイント
ヒアリングによって得た要望を、デザインや仕様に落とし込む際の注意点を以下にまとめます。
4‑1. ワイヤーフレームやモックで視覚化
言葉だけで伝え合うと誤解が生まれやすいので、できればワイヤーフレーム(ざっくりした構成図)やモックアップ(見た目に近いデザイン案)を準備しておきましょう。
クライアントに「ここはこう思ってますが、こうするのが一般的です」と選択肢を見せると議論が進みやすいです。
4‑2. モバイル(スマホ)優先視点を忘れずに
日本ではスマホ経由のアクセスが多いことを念頭に置き、スマホでの見え方・UI を最優先にすり合わせましょう。
PC デザインは “補完的” な役割と捉えるほうが無難です。
4‑3. UI/UX の導線設計
- ユーザーが迷わない導線(購入までのステップを極力簡潔に)
- ナビゲーションの優先順位(主メニュー・サブメニュー・フッター構成)
- CTA(Call to Action)ボタンの配置・文言・視認性
デザインだけでなく “使い勝手” を意識した会話をクライアントに促すことが重要です。
4‑4. フォールバック(代替案)を持っておく
ある機能が技術的に実現できない、コストが高すぎる、制限がある… といった局面は必ずあります。
事前に「この機能が難しいなら代替案はこういうものがあります」などのアイデアを持っておくと説明がスムーズになります。
4‑5. スコープの明確化と変更管理
「デザイン部分はここまで」「機能部分はこの範囲まで」「オプション機能は別途見積もり」など、範囲(スコープ)を明確に定義し、途中での仕様変更をどう扱うか(追加費用・再見積もり・スケジュール調整など)を最初から合意しておくことが肝心です。
5. 見積もり・工程・スケジュールのすり合わせ
案件の規模や複雑性に合わせ、見積もりとスケジュールをクライアントと精緻にすり合わせます。
5‑1. 工数見積もりとバッファ設計
機能設計・デザイン・コーディング・マークアップ・調整・テスト・修正… 各工程の工数を見積もり、さらにリスク対応の予備バッファ(10〜20%程度)を見込んでおくと安心です。
5‑2. マイルストーン設定
大きな段階で「デザイン確定」「コーディング完了」「ユーザーテスト」「最終確認」「納品」などのマイルストーンを設け、クライアントと共有します。
これにより、進捗管理や報告がしやすくなります。
5‑3. 支払いスケジュール
たとえば「着手金 30%」「途中検収後 40%」「最終納品後 30%」など段階分けするのが一般的です。
また、途中で仕様変更があった際の追加請求ルールも明示しておきましょう。
5‑4. リスク要因の洗い出し
遅延要因(素材の提供遅れ、レスポンス遅延、クライアントの決裁待ち、API 制限、デザイン変更多発など)を洗い出し、それぞれ対策を立てて事前にクライアントに共有しておくと信頼性が増します。
6. 契約条項・権利関係・納品物の取り決め
機能やデザインをつくるだけでなく、契約書・著作権・納品物・保守範囲などもきちんと取り決めましょう。
6‑1. 納品物の定義
- デザインデータ(Figma / Sketch / Photoshop など)
- HTML / CSS / JavaScript / テーマファイル
- 画像素材・アイコン・フォントデータ
- Shopify 設定データ(設定変更・テーマ設定)
- マニュアル(運用マニュアル/更新マニュアル)
- テスト結果・検収記録
これらを明文化しておかないと、「これは入っている/いない」の認識違いが生じやすいです。
6‑2. 著作権・権利帰属
デザインや素材・コードの著作権をどちらに帰属させるか(制作者に残す or クライアントに譲渡する)を明確にしておきます。
また、第三者素材(有料素材・写真・フォントなど)を使う場合、ライセンス条件も確認しておきましょう。
6‑3. 保守・運用・修正対応
- 納品後のバグ修正や保証期間/対応範囲
- 運用保守契約(別料金かどうか)
- 定期的なアップデート・バージョンアップ対応
- クライアントが将来追加したい機能を想定しておく条項
6‑4. 契約解除や中断条件
- クライアント都合での中断・キャンセル条件
- 制作者都合での契約解除条件
- 途中費用精算方法
クラウドソーシングサイトの実体と地雷案件について解説しています↓

7. 打ち合わせの進行術・ファシリテーション技法
どれだけ準備や内容が充実していても、打ち合わせの進行が拙ければ効果は薄れます。以下、実践的な進行術です。
7‑1. アジェンダ共有・時間管理
- 事前にアジェンダ(議題・時間配分)を示しておく
- 打ち合わせ冒頭にアジェンダを改めて確認
- タイムキープを意識し、「この議題はあと 5 分でまとめます」と区切る
7‑2. 双方向の対話を誘導
- 質問を投げかけて、クライアントにも思考させる(「こういう選択肢がありますが、どちらがいいでしょうか?」)
- 相手がぼんやり答えたら、選択肢を出して確認(Yes / No 型)
- なるべく “決められない” 状態を減らしていく
7‑3. 見える化ツールを活用
- 画面共有で仮案資料を見せながら議論
- リアルタイムにメモを共有(Google スライド・Notion・Miro・Google Docs など)
- フローチャートや構造図をその場で描く
7‑4. 恒常的に「確認」を入れる
「この認識で合っていますか?」「ここまでで質問はありませんか?」をこまめに挟むことで認識ずれを防ぎます。
また、クライアントがその場で納得しているかどうか、表情・反応を見てキャッチすることも大切です。
8. 打ち合わせ後のフォローアップ(議事録・確認・次ステップ)
打ち合わせが終わった後の “フォロー動作” が、プロジェクト成功への鍵を握ります。
8‑1. 議事録を速やかに作成・共有
- 決まったこと/未決定事項/次ステップ/担当者/期日 を整理
- クライアントにも確認してもらう(「この内容で相違ありませんか?」と返信をもらう)
- できれば 24 時間以内には共有する
8‑2. 誤解チェックと修正依頼
もし議事録の内容と記憶がズレていたら、早めに調整しておきましょう。
クライアントからの追加修正依頼・質問には丁寧に応答し、必要なら補足資料を添える。
8‑3. 次回打ち合わせ・納期確認
- 次回ミーティングの日時を確定
- マイルストーンに応じて、どの段階まで進めるかを双方確認
- 必要素材・情報(画像・商品データ・文言など)をクライアントに依頼
8‑4. リマインダ管理
進捗が滞らないよう、クライアント側の対応遅延を避けるためのリマインダ(期日のリマインドや進捗共有)を事前に設計しておくと効果的です。
9. よくあるトラブル事例と回避策
ここでは、私が実務上見た典型的なトラブルと、その予防策を紹介します。
| トラブル事例 | 発生原因 | 回避策 |
|---|---|---|
| クライアントから途中で「こういう機能を足したい」と要望 | スコープ未明確・仕様変更管理なし | スコープを最初に明文化、追加要望は別見積もり/変更手順を契約に盛る |
| クライアントが素材(写真・原稿)を出してくれない | クライアント側の準備不足 | 打ち合わせ時点で素材納期を明示し、遅延リスクを伝える |
| レスポンスが遅く進行不能になる | 決裁系の遅れ・クライアント多忙 | マイルストーン設定+リマインダ、クライアント側責任者を明確化 |
| デザイン完成後、「色味がちょっと違う」「イメージと微妙にずれている」と言われる | 初期段階でイメージのすり合わせ不足 | 参考サイト提示・モック提示・確認段階を複数設ける |
| 決済アプリや外部 API が導入できず仕様崩れ | 技術制約を事前に確認していなかった | 初期ヒアリング時に技術可否をチェック、代替案を持つ |
| 納品後の不具合・修正依頼延々 | 保守範囲と保証期間を契約で定めていなかった | 保守契約・保証対応の範囲・料金を明文化しておく |
こうした事例を依頼前にクライアントと共有しておくと、「ああ、そういうこともあるのか」という理解を得やすくなります。
10. まとめ:信頼関係と透明性を重視して進めよう
Shopify を使った Web 制作・デザイン案件では、技術力・デザイン力ももちろん大事ですが、“クライアントとの認識すり合わせ” がプロジェクトの成功率を大きく左右します。
打ち合わせの段階での丁寧な準備、双方向のヒアリングと対話、仕様・見積もり・納期・契約面の明文化、そしてフォローアップまで丁寧に実行することで、トラブルを防ぎ、安心してプロジェクトを進められます。
最後に、この記事の枠組みはあくまでテンプレートだと考えて、あなた自身のスタイルやクライアントの性質に合わせて微調整して使ってください。
Shopify公開前に確認すべきポイントを解説しております。納品の際に役立つと思いますので是非覗いて見てください↓
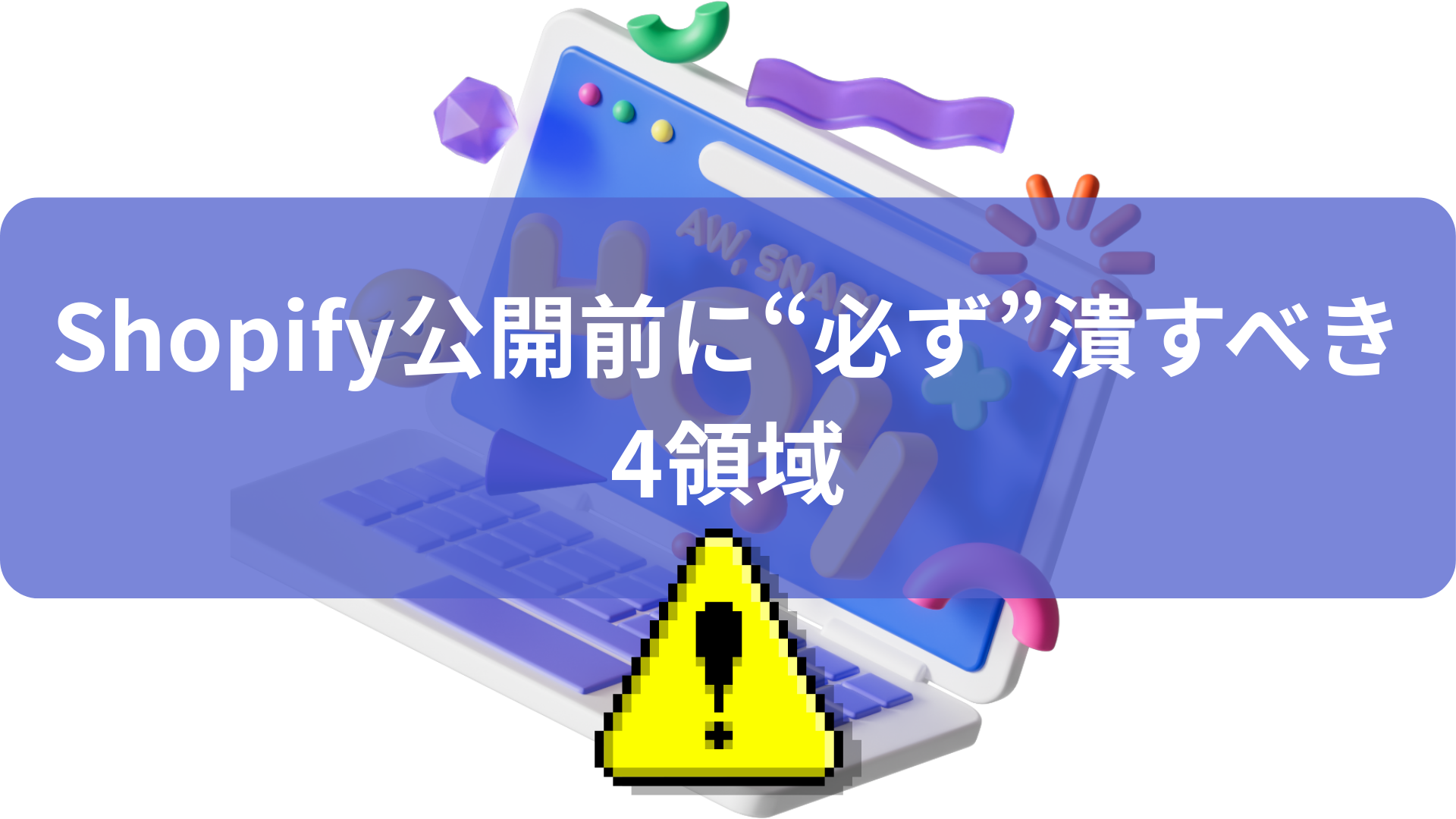
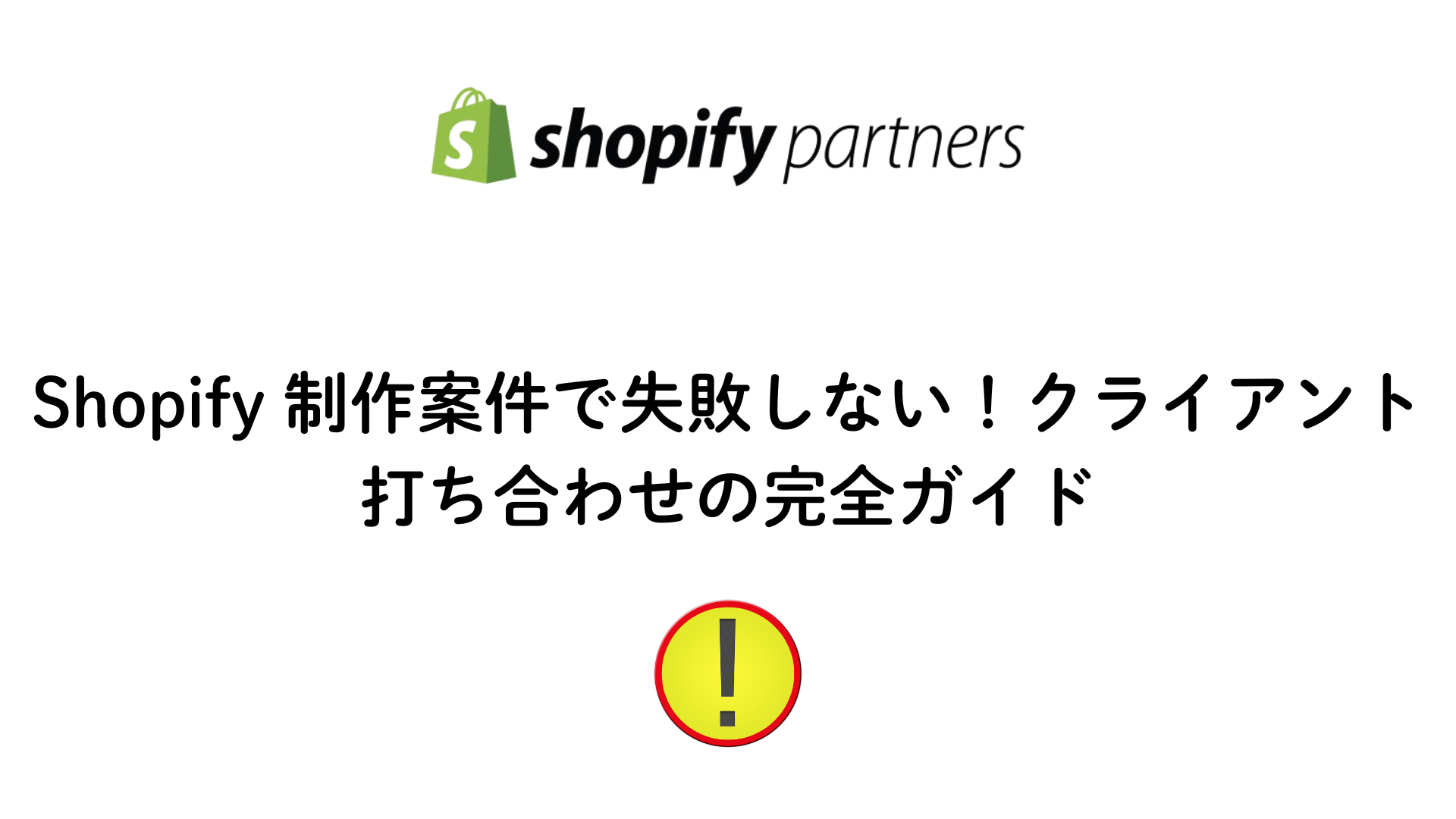
コメント