はじめに
Shopifyを学んでいると「Shopify エキスパート」という言葉を目にすることがあります。公式サイトにも「エキスパートに依頼すればストア構築がスムーズ」と書かれていて、ちょっと気になる存在。でも、実際にどんな仕組みで、どう関わるのがベストなのか、最初はよくわからない人も多いはずです。
僕自身、Shopify構築やWeb制作を副業として始めてから「エキスパートの存在感」を強く感じるようになりました。この記事では、Shopify エキスパートの概要から、実際に依頼するときの費用感、フリーランスとしてどう活用できるかまで、自分の経験を交えながら掘り下げてみます。
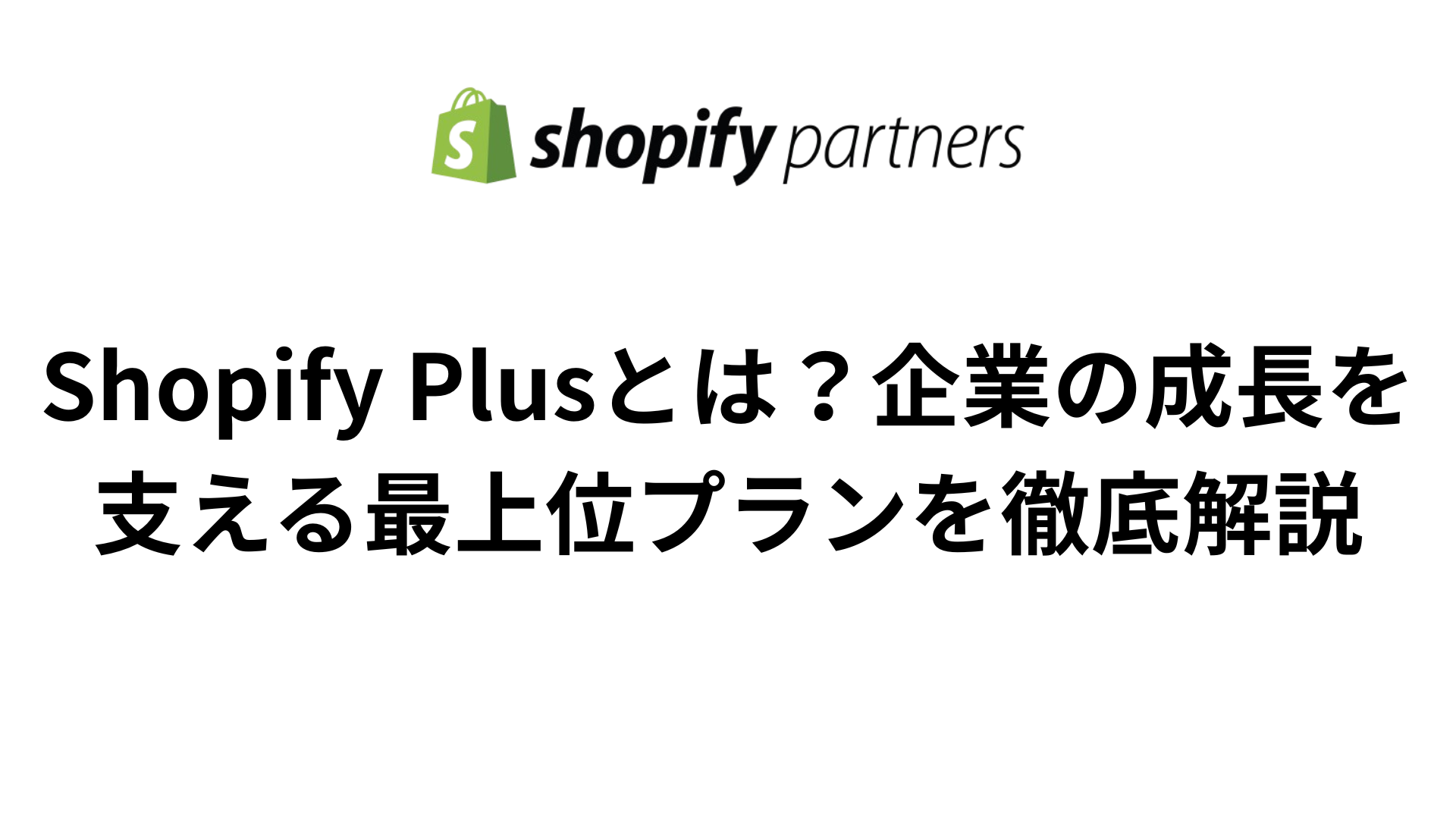
Shopifyエキスパートとは?
「Shopify エキスパート」とは、Shopifyが公式に認定したパートナーのことです。
- 公式認定 → Shopifyが審査を行い、信頼できるスキルを持ったパートナーだけが登録できる。
- サービス内容 → ストア構築、デザインカスタマイズ、アプリ開発、マーケティング支援など。
- クライアント向け → 初めてのストア立ち上げや大規模なリニューアル時に依頼することで安心感がある。
つまり「Shopify公式のお墨付きフリーランス/会社」といった感じですね。
エキスパートに依頼するメリット
実際に周りでもエキスパートに相談した人がいて、その話を聞くとメリットは大きいです。
- 安心感がある
公式認定なのでスキルや実績は保証されている。初心者が外注するなら失敗しにくい。 - 幅広い対応
テーマカスタマイズだけでなく、アプリ導入や海外販売サポートまで対応可能。 - スピードが早い
自分で調べて悩む時間を大幅に短縮できる。
ただし「便利だけど安くはない」というのが正直なところ。
費用感はどれくらい?
エキスパートに依頼する際の費用は案件によってバラバラですが、一般的に:
- 小規模(テーマ調整・商品登録代行など):5万円〜20万円
- 中規模(ストア構築一式):30万円〜80万円
- 大規模(独自アプリ開発・越境EC対応):100万円以上
僕も最初は「高いな」と感じましたが、裏を返せばそれだけ需要があり、ビジネスとして成立しているということ。
フリーランスから見たShopifyエキスパート
副業やフリーランスとして活動している人にとって、エキスパート制度は目標のひとつになると思います。
- 信頼性がアップ
「Shopify エキスパートです」と名乗れるだけで、クライアントからの信用度が全然違う。 - 案件獲得につながる
公式サイト経由で問い合わせが来るケースもある。 - 長期的なキャリアになる
単発の案件ではなく、運用・改善を含めて長く付き合えるクライアントが増える。
僕自身も「いずれはエキスパートを目指したい」と思っていて、そのために案件経験を積んだり、海外クライアントともやり取りを増やしています。
実際にエキスパートに依頼した事例(周囲の話)
- アパレルブランドのケース
→ デザインにこだわりたいと相談し、テーマのカスタマイズから撮影ディレクションまで依頼。結果、初月の売上が想定の2倍になった。 - 食品ECのケース
→ 自社で始めたが在庫連携や配送設定でエラー続き。エキスパートに依頼し、システム周りを整備してスムーズに。
どちらも「自力でやっていたら時間がかかりすぎていた」という話を聞きました。
フリーランスがエキスパートを活用する方法
エキスパートに直接なるのは難易度が高いですが、「うまく関わる」ことはできます。
- エキスパートの下請けとして経験を積む
- 自分はデザイン、エキスパートにシステムを依頼という協業スタイル
- ブログやSNSで発信してエキスパートとつながる
「いきなり自分がエキスパートになる」のではなく、「エキスパートと一緒に動く」ことも選択肢としてありです。
Shopifyエキスパートを目指すには?
- 実績を積む:ストア構築経験を増やす
- 英語力を磨く:海外クライアントや資料対応に必須
- マーケティング知識を学ぶ:単なる構築だけではなく「売れる仕組み作り」ができると強い
最終的にShopifyの公式パートナー申請を行い、審査を通過すればエキスパートの仲間入りです。
まとめ
「Shopify エキスパート」とは、ただのスキル証明ではなく信頼と案件の入り口を手にする仕組み。
フリーランスや副業で活動している人にとっては、最終目標にしてもいいし、協業のパートナーとして関わるのもあり。
僕自身も、エキスパートを意識することで「自分の強みはどこか?」「何を伸ばせば仕事になるのか?」が明確になってきました。
もしこれからShopifyを学んでいる人がいたら、ぜひ「エキスパート」という仕組みを知っておくとキャリアの見通しが広がりますよ。




コメント